[遠州掛塚 貴船神社祭礼][貴船神社]
更新日:2003年6月12日(木曜日) |
| ●貴船神社 |
 |
| 貴船神社 |
 |
|
|
|
|
|
|
| 御 祭 神 |
たかおかみのかみ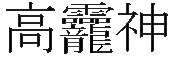 |
| ※以後、おかみと略す。 |
|
|
|
|
|
|
| 御 神 徳 |
| 御祭神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)の御子に坐しまして、畏くも伊勢内宮の天照大神(あまてらすおおみかみ)とは御兄弟であらせられます。 この御祭神は、水に関する一切の支配を司り給いて、農業・林業・漁業・醸造業・航海業の守護に高く広い御神徳を有し、古来炎旱、霖雨、冷涼、暴風雨による凶作、其の他 天下に大事ある時は萬民こぞって祈念を寄せ、特に天竜川河口掛塚港鎮守として、廻船業者の崇敬の厚いお社であります。 |
|
|
| 由 緒 |
本社の鎮座の年代は詳らかではありませんが、室町時代以前の創立と伝えられます。 天正4年(1576)に社殿の再建を行いましたが、この社殿は明治16年(1883)9月6日の火災に罹り境内樹木と共にすべて焼失してしまいました。 其の後、本殿は明治20年(1887)、拝殿及び幣殿は明治30年(1897)に再建されました。 更に昭和10年(1935)には幣殿の増築を行い、昭和62年(1987)に御本殿鞘堂を創建され現在に至って居ります。 天正4年(1576)に社殿の再建を行いましたが、この社殿は明治16年(1883)9月6日の火災に罹り境内樹木と共にすべて焼失してしまいました。 其の後、本殿は明治20年(1887)、拝殿及び幣殿は明治30年(1897)に再建されました。 更に昭和10年(1935)には幣殿の増築を行い、昭和62年(1987)に御本殿鞘堂を創建され現在に至って居ります。
社領としましては、慶安元年(1648)10月24日、徳川家光公より朱印地8石の寄進がありました。明治6年(1873)10月24日には郷社に列せられ、明治40年(1907)1月12日、神撰幣帛料供進社に指定され、第1次供進使として磐田郡長 桑原楯雄殿が例祭に参向しています。 郡制廃止により昭和5年以来6回に亘り、静岡県庁より幣帛供進使として、県知事代理が大祭に参向になりました。昭和56年(1981) 7月1日、県内神社級別より5級社指定され現在に至っております。 |
|
|
| 社 号 |
| 往古は多く貴布祢明神、または貴布祢神社と記し、又木船、黄船等の文字が諸書に見えます。明治4年、大政官達を以て現在の貴船に定められました。 静岡県に貴船神社の数は29社で、県西部(遠江)に20社あり、特に天竜川筋に多く祀られております。 |
|
|
| 境 内 |
 旧境内地は4反4畝29歩、国有境内地でありましたが、現境内地1162坪9合4勺は、昭和24年12月25日、国有境内地無償譲与の許可を得、昭和26年3月25日に登記を完了しました。 旧境内地は4反4畝29歩、国有境内地でありましたが、現境内地1162坪9合4勺は、昭和24年12月25日、国有境内地無償譲与の許可を得、昭和26年3月25日に登記を完了しました。
境内には、往昔古木欝蒼として枝を交えて高く中天に聳え、極めて森厳でありました。明治年間、数度の火災に罹り痛く其の風致を損じましたが、明治37、8年戦争後になって、戦捷記念庭園とする計画をたてて、漸次樹木を配植してより、年と共に繁茂し旧に復し、再び崇高の観を添える状となり現在に至って居ります。 |
|
|
社 殿
及び
建造物 |
|
本 殿 |
神明造り銅板葺 |
明治20年9月建築 |
|
幣 殿 |
平屋造り亜鉛板葺 |
昭和10年12月建築 |
|
拝 殿 |
入母屋造り銅板葺 |
明治30年9月建築 |
|
社 務 所 |
平屋造り瓦葺 |
大正12年9月建築 |
|
宝 庫 |
2階建瓦葺 |
大正10年移転修理 |
|
鳥 居 |
花崗岩 |
|
|
水 屋 |
銅板葺 |
昭和38年建築 |
|
本社玉垣 |
檜造 |
昭和10年12月建築 |
|
唐 獅 子 |
花崗岩1対 |
大正6年9月建築 |
|
石 燈 籠 |
花崗岩2基 |
明治30年建築 |
|
〃 |
〃 |
明治40年建築 |
|
倉 庫 |
平屋建瓦葺 |
明治32年9月建築 |
|
〃 |
煉瓦造瓦葺 |
明治43年4月建築 |
|
〃 |
2階建瓦葺 |
大正6年移転 |
|
御池玉垣 |
御影石 |
昭和4年6月建築 |
|
幟 立 |
御影石 |
昭和3年9月建築 |
|
|
| 宝 物 |
|
御 鏡 |
直径 1尺2寸
直径 5寸 |
元禄10年8月、遠州掛塚村廻船中寄附 |
|
扁 額 |
貴布祢神社 |
正五位山岡鉄太郎筆槻板に彫刻
津倉世雄寄附 |
|
神 額 |
貴船神社 |
従一位大勲位公爵徳大寺実則郷筆
大正4年11月 尾崎孝三郎奉納 |
|
御 船 |
壱 |
宝暦11年6月11日、当村新町若者中 |
|
御 面 |
桐製12種 |
文化2年9月、江戸国東港町 |
|
御 神 輿 |
壱 |
明治14年再建
寛延元年8月吉日 翠簾幕、御道具 |
|
旧御神輿 |
壱 |
建造年不詳
宝永4年 漆塗り
文政1年 漆塗り替え |
|
朱 印 状 |
九 |
| 徳川家光朱印状 |
| |
遠江国豊田郡懸塚郷 貴布祢神社
領同所内8石事任先規寄附之訖全可収納
并社中竹木諸投等免除如有来永不可相違者也
慶安元年10月24日
家光朱印 |
| 徳川綱吉朱印状 |
| |
遠江国豊田郡懸塚郷 貴布祢明神
社領同所之内8石事任 慶安元年
10月24日先判之●寄附之訖全可収納并社
中竹木諸等免除如有来永不可相違者也
貞享2年6月11日
綱吉朱印 |
| 徳川吉宗朱印状 |
| |
遠江国豊田郡懸塚郷 貴布祢明神
社領同所之内8石事并社中竹木諸投等免除
如依富み家光先判之例永不可有違者也
享保3年7月11日
吉宗朱印 |
| 以下同朱印内容 |
| |
| 延享 4年 8月11日 |
家重 |
| 宝暦12年 8月11日 |
家治 |
| 天明 8年 9月11日 |
家斎 |
| 天保10年 9月11日 |
家慶 |
| 安政 2年 9月11日 |
家定 |
| 蔓延 1年 9月11日 |
家茂 |
|
|
|
|
祭 礼
と
屋 台 |
| 天文年代(1532-1554)、遠州第1の名港 掛塚湊の発展と共に、廻船業者を始め漁業者の信仰により徳川時代の中期頃、神輿の渡御に続いて氏子の若衆が屋台を曳き、神輿のお供をしたことから始まりだと伝えられております。 最初の屋台は2階造りで曳舞台に大きなダシを作ったものです。 このダシの作成には、3ヶ月から半年も掛かって随分見事なものであったと伝えられています。 昔はこのダシを見るのが目的で、掛塚の屋台は『1度見ぬも馬鹿、2度見るも馬鹿』と云われ、この言葉は屋台にあらずしてダシを云ったものです。 徳川末期に至って屋台が改造され。各町共唐破風造り1階建ての屋台に変わり、現在『掛塚屋台まつり』として、東海随一を誇る屋台は本舞台9台、曳舞台6台で、金箔・漆を塗り周囲には信州諏訪の立川和四郎・尾張の早瀬長兵衛の弟子を始めとする各地の名工の刻んだ彫刻と、天下に類例のない現代人の及ばない程の精巧な刺繍を施した天幕で飾りつけられられ、静岡県無形民俗文化財にも指定されているお囃子(掛塚祭屋台囃子)の笛太鼓に合わせ各町から曳き出して貴船神社の神前に集合する屋台は徳川時代から明治にかけての芸術的枠を集めたもので、二日間にわたって曳き廻す光景は壮重奇麗、絢爛豪華な絵巻物が展開されます。 |
|
|
|
|
|
| 参考 : |
貴船神社のしおり
貴船神社宮司 関正胤様 |
All Rights Reserved, Copyright (C) noboru.ohta.
2002. |